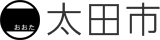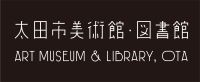本文
第5回下水道講座 (1)下水道法制度の移り変わり
まず、「雨水」や「汚水」を排水するために始められた下水道事業について、その背景と下水道法制度の移り変わりについて見ていきましょう。
| 背景 | → | 下水道法制度の移り変わり |
|---|---|---|
| コレラの流行、浸水被害 | 土地の清潔を守る |
明治33年3月 旧下水道法制定 ※「土地の清潔の保持」を目的 |
| 生活環境への関心の高まり |
都市の健全な発達 公衆衛生の向上 |
明治33年4月 新下水道法制定 ※「都市の健全な発達」 「公衆衛生の向上」 を目的 |
| 河川、海などの水質の悪化 |
河川・海等の水質保全 |
明治45年12月 下水道法改正(以下法改正) ※「公共用水域の水質保全」を目的 ・処理場の設置義務化 ・流域下水道制度の創設 他 |
| 省エネ・リサイクル社会の到来 |
下水道資源の有効利用 |
平成8年6月 法改正 ・汚泥の原料処理の努力義務化 ・光ファイバー設置の規制緩和 |
| 水質改善を求める声など | 水質改善 |
平成15年9月 法改正 ・合流式下水道の改善の義務化 ・計画放流水質を規定 |
|
都市型水害の頻繁 進まない閉鎖性水域(湖や沼など)の水質改善 |
広域的な雨水の排除と高度処理 |
平成17年6月 法改正 ・雨水流域下水道制度の創設 ・事故時の措置の義務づけ 他 |
| 地域主権改革の推進 | 地方の自主性の向上 |
平成23年5月、8月 法改正 ※地域の自主性および自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律 ・事業計画の認可制度を協議制度へ 他 |
|
集中豪雨などによる浸水被害 適切な下水道管理の推進 再生可能エネルギー活用推進 広域化の推進 |
官民連携の浸水対策 下水道機能の持続的確保 再生可能エネルギーの活用 |
平成27年5月 法改正 ・雨水公共下水道制度の創設 ・浸水被害対策区域制度の創設 ・雨水貯留施設の管理協定制度の創設 ・汚泥等の再利用の努力義務化 ・広域化、共同化を促進するための協議会制度の創設 他 |
(国土交通省「令和2年7月下水道政策研究委員会 制度小委員会報告書」参考)