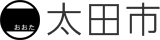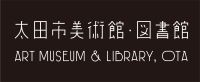本文
水田活用の直接支払交付金「水張り5年ルール」の見直しについて
水田活用の直接支払交付金における交付対象水田の見直しについて(水張り5年ルール)
国の経営所得安定対策等実施要綱が改正され、畑作物の生産が定着している水田は畑地化を促す一方、水田機能を維持しながら、麦・大豆・野菜などの畑作物を生産する農地については、水稲とのブロックローテーションを促す観点から「令和4年度から令和8年度までに、一度も水張りを行っていない水田」と「水張りを行った翌年から5年間に、一度も水張りを行っていない水田」については「水田活用の直接支払交付金の交付対象農地から外す」取扱いとされていました。
令和9年度から、水田政策の見直しされることになります。水田を対象として支援する水田活用の直接支払金を、作物ごとの生産性向上等への支援へと転換します。このため、令和9年度以降は「水張り5年」の要件は求めないことになりました。
令和7・8年度は、水稲を作付可能な田について、連作障害を回避する取組を行った場合、水張りしなくても交付対象とします。
令和9年度から、水田政策の見直しされることになります。水田を対象として支援する水田活用の直接支払金を、作物ごとの生産性向上等への支援へと転換します。このため、令和9年度以降は「水張り5年」の要件は求めないことになりました。
令和7・8年度は、水稲を作付可能な田について、連作障害を回避する取組を行った場合、水張りしなくても交付対象とします。
経営所得安定対策について【農水省HP】<外部リンク>
水田活用の直接支払交付金について【農水省HP】<外部リンク>
水張り5年ルールの見直し内容
令和7・8年度の対応として、以下のいずれかの取組を行った場合は、水稲の作付が行われたものとみなします。
(1)湛水管理を1ヶ月以上実施したことが確認できること
(2)連作障害を回避する取組(土壌改良資材・有機物(堆肥・もみ殻等を含む)の施用・土壌に係る薬剤の散布・後作緑肥の作付・病害虫抵抗性品種の作付)
(1)湛水管理を1ヶ月以上実施したことが確認できること
(2)連作障害を回避する取組(土壌改良資材・有機物(堆肥・もみ殻等を含む)の施用・土壌に係る薬剤の散布・後作緑肥の作付・病害虫抵抗性品種の作付)
対象水田にて水稲作付を行う場合
作付けが可能な圃場は水稲(主食用米(うるち、もち)、飼料用米、米粉用米、加工用米、稲発酵粗飼料用稲(W C S用稲))の作付けを行ってください。
水田台帳の作付計画を基に、夏頃に再生協議会職員が現地確認を実施します。
※近年、自然災害・気候変動による収量・品質の低下が発生しています。農業経営安定化のため、農業共済保険への加入もご検討ください。
水田台帳の作付計画を基に、夏頃に再生協議会職員が現地確認を実施します。
※近年、自然災害・気候変動による収量・品質の低下が発生しています。農業経営安定化のため、農業共済保険への加入もご検討ください。
湛水管理を実施する場合
水張り(水稲を作付けせずに、1か月以上の湛水管理によるみなし措置)を実施する方は、水田台帳の対象圃場の「水張り実施」欄に1を記入して提出してください。
1か月以上の湛水管理を実施した方は、
(1)湛水管理開始・終了の年月日記入の作業日誌
(2)湛水管理開始時・終了時の圃場の写真(水が張ってある状態)
を再生協議会まで提出してください。
※水田台帳に水張り実施「1」を記入した方には地名地番が記載された作業日誌を送付します。
※圃場写真の裏面に農業者氏名、作業日誌のほ場番号、撮影日を記入してください。
※連作障害によって収量が低下した圃場は実施しないでください。
1か月以上の湛水管理を実施した方は、
(1)湛水管理開始・終了の年月日記入の作業日誌
(2)湛水管理開始時・終了時の圃場の写真(水が張ってある状態)
を再生協議会まで提出してください。
※水田台帳に水張り実施「1」を記入した方には地名地番が記載された作業日誌を送付します。
※圃場写真の裏面に農業者氏名、作業日誌のほ場番号、撮影日を記入してください。
※連作障害によって収量が低下した圃場は実施しないでください。
連作障害を回避する取組を実施した場合
連作障害を回避する取組を実施する方は、取組の根拠資料として作業日誌や栽培記録簿、資材の購入伝票等を提出できるよう保管しておく必要があります。