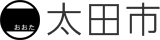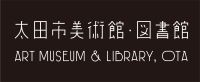本文
国民年金の届け出と納付
国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入し、加入者(被保険者)は第1号、第2号、第3号の3種類に区分されます。
- 第1号被保険者・・・自営業者や学生など
- 第2号被保険者・・・厚生年金や共済組合に加入している人(会社員や公務員など)
- 第3号被保険者・・・第2号被保険者に扶養されている配偶者(専業主婦など)
国民年金加入の手続き
次の場合には、国民年金第1号加入手続きが必要です。
| こんなとき | 用意するもの |
|---|---|
| 会社を退職したとき | 社会保険離脱証明書、基礎年金番号通知書(年金手帳)、マイナンバー(通知)カード、本人確認のできるもの ※口座振替で納付希望の場合は振替口座の通帳と届出印 |
| 第2号配偶者に扶養されなくなったとき ※離婚、配偶者の退職、あなたの収入が増えた場合など |
国民年金保険料の額(令和7年4月1日現在)
- 定額保険料 月額17,510円
- 付加保険料 月額 400円(希望により第1号被保険者および任意加入被保険者が納付し、老齢基礎年金の年額に上乗せで受給できます。上乗額=200円×付加保険料納付月数)
保険料の納付方法
- 現金納付(納付書でのお支払い)
「領収(納付受託)済通知書」(納付書)を使用し、「納付期限」までに銀行などの金融機関、郵便局、コンビニエンスストアにて納めてください。手元に納付書がないときは、年金事務所で納付書の再発行が必要です。 - 口座振替
口座振替で納めると手間がかからず、納め忘れを防ぐこともできます。申込み手続きは、太田市役所または年金事務所、金融機関の窓口で受け付けています。 - クレジットカード納付
クレジットカードにより定期的に納付する方法です。申込み手続きは、太田市役所または年金事務所で受け付けています。 - 電子決済(スマートフォンアプリ)での納付
「領収(納付受託)済通知書」(納付書)のバーコードを読み取り、決済アプリで納付する方法です。
詳しい利用方法は日本年金機構のホームページ(ここをクリック)<外部リンク>をご覧ください。 - 電子納付(Pay−easy)での納付
「領収(納付受託)済通知書」(納付書)に記載されている「収納機関番号」、「納付番号」、「確認番号」をPay-easy対応のATMやインターネットバンキングの画面に入力して納付する方法です。
詳しい利用方法は日本年金機構のホームページ(ここをクリック)<外部リンク>をご覧ください。
保険料の前納割引制度
保険料を納付期限内にまとめて前納すると、割引になります。
口座振替による前納
- 2年前納(4月~翌々年3月分) ※2年で約17,000円割引
- 1年前納(4月~翌年3月分) ※1年で約4,000円割引
- 6カ月前納(4月~9月分、10月~翌年3月分) ※6ヶ月で約1,000円割引
- 当月末振替 ※月額60円割引
- 翌月末振替 ※保険料の割引はありません。
現金(またはクレジットカード)による前納
現金またはクレジットカードでまとめて前納(上限は2年分)すると、割引になります。現金の場合は前納納付専用の納付書が必要となります。また、クレジットカード納付の場合は申込みが必要になりますので、太田市役所または年金事務所までお問い合わせください。
※前納についてはいつでもお申込みができ、開始時から年度末(または翌年度末)までの保険料をまとめて振替ができます。
詳しい割引額などは日本年金機構のホームページ(ここをクリック)<外部リンク>をご覧ください。
保険料が納められない時は
保険料免除制度(全額免除・4分の3免除・半額・4分の1免除)
経済的な理由等で保険料を納めることができないときは、申請し、承認されると保険料が免除される制度で、(1)全額免除(2)4分の3免除(3)半額免除(4)4分の1免除があります。
平成21年度4月分より国庫負担割合が変わりました。
(1)全額免除を受けた期間は、老齢基礎年金が8分の4の受給となります。
(2)4分の3免除を受けた期間は、老齢基礎年金が8分の5の受給となります。
ただし、4分の1の保険料を納めない場合は未納期間として取り扱われますのでご注意ください。
(3)半額免除を受けた期間は、老齢基礎年金が8分の6の受給となります。
ただし、半額の保険料を納めない場合は未納期間として取り扱われますのでご注意ください。
(4)4分の1免除を受けた期間は、老齢基礎年金が8分の7の受給となります。
ただし、4分の3の保険料を納めない場合は未納期間として取り扱われますのでご注意ください。
学生納付特例制度
学生本人の所得が一定額以下の場合、申請し、承認されると保険料の納付が猶予される制度です。この制度の対象者は、大学、短大、専門学校等に在籍している学生です。納付特例を受けた期間については、年金を受け取るための期間として計算されますが、年金額には反映されません。
納付猶予制度
50歳未満の方で本人、配偶者の前年あるいは前々年の所得(申請した時期によって異なります)によって納付が猶予されます。申請免除と違い世帯主に所得があっても本人、配偶者だけの所得だけで審査します。
納付猶予を受けた期間については、年金を受け取るための期間として計算されますが、年金額には反映されません。
※なお、免除期間、学生納付特例期間とも10年以内に保険料を追納することができ、追納されますと減額されずに年金を受け取ることができます。
| 問い合わせ先 |
日本年金機構 太田年金事務所 |
|---|