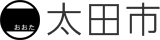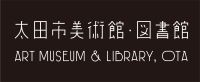本文
『太田かるた』絵札・読み札か行
| 絵札 | 読み札 | 解説 |
|---|---|---|
 |
 |
金山城は、文明元年(一四六九)に新田氏一族の岩松家純によって築かれた山城で、その後城主は下克上により、横瀬(後の由良)氏に代わりましたが、天正十八年(一五九〇)の廃城まで難攻不落を誇った山城として知られています。金山城は国指定史跡で、活用のための総合的な調査と整備が進められています。金山の大ケヤキは金山城の御台所曲輪にあり、推定樹齢は六〇〇年とも八〇〇年ともいわれ、金山城の歴史を見守った大ケヤキとして知られています。 |
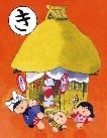 |
 |
日光例幣使道一三宿の一宿場であった木崎宿は、天保十四年(一八四三)には本陣や旅籠屋が三三軒もあるにぎやかな宿場でした。宿場はずれの長命寺門前に、子育て地蔵が寛延三年(一七五〇)に建立されました。越後国(新潟県)などから木崎宿に売られてきた飯売女たちの信仰を受けたことから色地蔵として広く知られるようになりました。 |
 |
 |
太田市は江戸時代には日光例幣使道の宿場町として発達し、大正期以降は中島飛行機の、第二次大戦後は富士重工業(株)の企業城下町として栄えました。現在は輸送用機械、電機、金属、プラスチックス、繊維等を中心に企業活動が行われ、基幹産業が集積して北関東有数の工業都市として着実に発展しています。現在、工業製品出荷額等は一兆八千億円を超えて県下第一位で、両毛エリアを代表する都市でもあります。 |
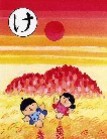 |
 |
この古墳は太田駅東方約一キロメートルの平地に築造されています。別名を男体山ともいい、墳丘全長二一〇メートルで、東日本では最大、全国でも二六位の規模を誇る大前方後円墳です。周囲には二重の周堀が巡らされ、北東と西に陪塚をもちます。大型の長持形石棺の一部が露出し、縄懸突起が確認できます。埴輪は、家形埴輪・水鳥形埴輪や円筒埴輪などが出土しています。築造時期は五世紀中頃と推定され、被葬者は畿内大和政権と強いつながりを持っていた毛野国の大首長と考えられています。 |
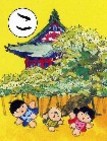 |
 |
金山南麓にある大光院は「子育て呑龍」の名前で親しまれています。正しくは義重山新田寺大光院といいます。大光院は徳川家康が新田氏の祖新田義重を追善供養するために慶長十八年(一六一三)に建立した寺です。「呑龍」とは、大光院を開山した呑龍上人のことです。上人は貧しい子どもたちを弟子という名目で養育したといわれています。この縁をもって「七ツ坊主」という風習が生まれました。これが「子育て呑龍」の由来です。本堂前の黒松は開山上人お手植えの松と伝えられ、その形から「臥龍松」といわれています |