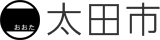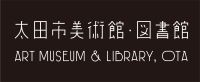本文
確定申告書(第二表)「住民税に関する事項」の記載漏れにご注意ください
確定申告書(第二表)「住民税に関する事項」の記載漏れにご注意ください
所得税等の確定申告をする方は、その確定申告書が税務署から市町村にデータ送信されますので、改めて市・県民税の申告書を提出する必要はありません。
ただし、次の事項については、所得税等と市・県民税とでは取り扱いが異なるため、確定申告書「住民税に関する事項」欄(第二表下部)へ該当事項があれば記入をしてください。
※記入がない場合、市・県民税(住民税)が正しく計算されない場合がありますのでご注意ください。
(1)扶養親族に係る住民税に関する事項
- 同一生計配偶者
あなたの合計所得金額が1,000万円超であり、かつ生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が
48万円以下の場合、配偶者の氏名・個人番号・生年月日を記入し、「同一」に◯をしてくださ
い。
- 16歳未満の扶養親族
16歳未満の扶養親族がいる場合、当該扶養親族の氏名・個人番号・続柄・生年月日を記入し、「1
6」に◯をしてください。16歳未満の扶養親族についての扶養控除額はありませんが、住民税の非
課税限度額制度の適用に影響があります。
- 別居の扶養親族
別居の扶養親族がいる場合、「別居」に◯をしてください。また、下段の(10)欄にも氏名と住
所も記入してください。
(2)配当に関する住民税の特例
所得税において確定申告不要制度を選択した非上場株式の少額配当等がある場合は、こちらに申告書第一表の配当所得の金額と確定申告不要制度を選択した非上場株式の少額配当等の金額を合計した金額を記入してください。
住民税には、当該申告不要制度がありませんので申告が必要となり、他の所得と総合して課税されます。
(3)非居住者の特例
確定申告をする年分の翌年の1月1日現在、日本に住所を有する方で前年中に非居住者期間を有する方は、その期間中に生じた国内源泉所得のうち所得税で分離課税された金額を記入してください。他の所得と総合して住民税が課税されます。
(4)配当割額控除額
上場株式等に係る配当所得等について申告することを選択した場合は、こちらに特別徴収された住民税額を記入してください。
住民税の年税額を計算した結果、税額控除又は還付されます。
(5)株式等譲渡所得割額控除額
源泉徴収口座での上場株式等に係る譲渡所得について申告することを選択した場合は、こちらに特別徴収された住民税額を記入してください。
住民税の年税額を計算した結果、税額控除又は還付されます。
(6)住民税の徴収方法の選択
給与・公的年金等に係る所得以外(当該年度の4月1日において、65歳未満の方は給与所得以外)の所得に係る住民税について、その徴収方法を選択することができます。
- 給与からの特別徴収を希望する場合には、「給与から差引き」に〇を記入し、納付書や口座引き落としなど自分で納付することを希望する場合には、「自分で納付」(普通徴収)に〇を記入してください。
- 給与・公的年金等に係る所得以外(該当年度の4月1日において65歳未満の方は給与所得以外)の所得が無い方は、こちらの欄に記入する必要はありません。
(7)寄附金税額控除
以下について、それぞれの合計寄附金額を記入してください。
- 都道府県、市区町村への寄附
・ふるさと納税
・最終的に被災地に拠出される日本赤十字社や中央共同募金会などが募金している災害義援金等 - 住所地の共同募金、日赤支部
- 都道府県条例指定寄附
・住所地の県が条例で指定した団体への寄附 - 市区町村条例指定寄附
・住所地の市区町村が条例で指定した団体への寄附
(8)退職所得のある配偶者・親族
前年中に退職所得のある配偶者又は親族等の合計所得金額を退職所得を除いた上で計算した結果、あなたが個人住民税の配偶者(特別)控除、扶養控除を受けることができる場合には、その配偶者又は扶養親族等の氏名・マイナンバー(個人番号)・続柄・生年月日・前年中の退職所得を除いた合計所得金額を記入してください。
(9)別居の控除対象配偶者・控除対象扶養親族・事業専従者の氏名・住所
(1)の控除対象配偶者・控除対象扶養親族・事業専従者のうち、別居している方がいる場合は、こちらに氏名・住所を記入してください。
(10)所得税で控除対象配偶者などとした専従者
所得税で一定の理由に基づき専従者給与届出書を提出しないで配偶者控除や扶養控除の対象とした方を、住民税や事業税では青色事業専従者とすることができます。(青色事業専従者の要件は、所得税の場合と同様です。また青色事業専従者給与額に関する事項を記載した市・県民税申告書の提出が必要です。)これに該当する専従者がある場合には、その方の氏名と給与の額を記入します。