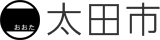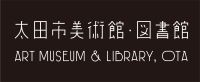本文
休泊行政センター|八重笠沼

邑楽町と大泉町に接する八重笠地区には、古代から大きな沼があったという。低湿地帯で雑木林につつまれた水と緑の里である。沼は堤防等で治水事業が進められ、釣堀として、太公望達の憩いの場になっている。

八重笠沼の歴史を紐解く時、その名の由来がわかる。正保年間(1644~1648年)。
この頃は、館林藩主松平氏が龍舞町の検地を行ない、八重笠村から分かれた時期と一致する。

それでは話を進めてみよう。
龍舞の修験者、松本院清安(せいあん)という人が、この沼に釣糸を垂れていた時の事である。
足元に姿は小さいが眼を妖しく光らせた蛇が近づいて来た。
そして、清安の足を舐め始めた。

なにやら怪しく思ったのか、清安は身に付けていた伝家の名剣で、これを刺した。
すると一天にわかにかき曇り、ものすごい豪雨になった。
この雨は「八つの笠を重ねてやっと止んだ」という話が残りそれが沼の名前になったという。

この剣は、龍舞にある賀茂神社に保管されていると伝えられている。
また、この蛇というのが、八重笠沼の北にある日枝神社の古池に住んでいたもので、この池と八重笠沼は横穴で繋がっていたという話だ。