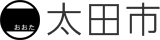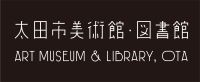本文
新田荘遺跡(重殿水源)
 太田市の北西部は大間々扇状地に立地していることから、扇端部の標高60mの地点を中心として多くの湧水が見られます。重殿水源は、現状では、周囲を民家や工場に囲まれ、四方を石垣とコンクリートで護岸された東西10m、南北23mの小さな池です。北西の角には3基の石のほこらがあり、かつての面影をうかがうことができます。この東側には一級河川、大川の源流であることを示す標柱が立てられています。
太田市の北西部は大間々扇状地に立地していることから、扇端部の標高60mの地点を中心として多くの湧水が見られます。重殿水源は、現状では、周囲を民家や工場に囲まれ、四方を石垣とコンクリートで護岸された東西10m、南北23mの小さな池です。北西の角には3基の石のほこらがあり、かつての面影をうかがうことができます。この東側には一級河川、大川の源流であることを示す標柱が立てられています。
元亨2年(1322)の「関東裁許状」(正木文書)によると、大館宗氏と岩松政経が「一井郷沼水」から流れ出た「用水堀」を巡って争論を起こしたことに対して、鎌倉幕府が判決を下したことが分かります。この古文書にある「一井郷沼水」が重殿水源であると考えられています。
新田荘は大間々扇状地の扇端部に位置していることから豊富な湧水に恵まれ、荘園を経営するために湧水が利用されたと考えられています。かつては実際に市野井・金井・赤堀・木崎など多くの地域がこの水を農業用水として利用していました。重殿水源はこういったことを証明する貴重な史跡です。
| 指定区分 | 国指定史跡[遺跡地] |
|---|---|
| 指定年月日 | 平成12年11月1日 |
| 所在地 | 太田市新田市野井町1472-1地先 |
地図の読み込みに関する問題が発生したとき<外部リンク>