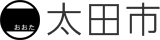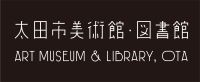本文
曹源寺栄螺堂
 祥寿山曹源寺(しょうじゅさんそうげんじ)は曹洞宗の寺院で、寺伝によると新田氏の祖義重が京都から迎えたという養姫である祥寿姫の菩提を弔うため、文治3年(1187)に開基したと伝えられています。また、境内には薗田氏一門により造立されたと考えられる名号角塔婆や中興開基と伝えられる横瀬氏の五輪塔があります。
祥寿山曹源寺(しょうじゅさんそうげんじ)は曹洞宗の寺院で、寺伝によると新田氏の祖義重が京都から迎えたという養姫である祥寿姫の菩提を弔うため、文治3年(1187)に開基したと伝えられています。また、境内には薗田氏一門により造立されたと考えられる名号角塔婆や中興開基と伝えられる横瀬氏の五輪塔があります。
江戸時代に本堂が火災に遭い、その後、観音堂が造られ、観音堂を本堂としています。観音堂は栄螺堂(さざえどう)と呼ばれ、江戸時代中期に普及・発展した三十三観音・百観音信仰を背景に、関東・東北地方に限って建造された三匝堂(さんそうどう)のひとつです。寛政10年(1798)に創建された建物で、間口・奥行ともに9間(約16.3m)、高さ55.5尺(約16.8m)であり正面は東向きです。外観は重層の二階建に見えますが、内部は三層になっています。堂内には秩父、坂東、西国の観音札所計百ヵ寺の観音像を安置し、右回りに堂内を一方通行で巡拝できることから「栄螺堂」の名があります。現在、埼玉県本庄市の成身院、福島県会津若松市の旧正宗寺、茨城県取手市の長禅寺などがありますが、曹源寺の栄螺堂が最大です。
参拝等については直接、曹源寺にお問い合わせください。
曹源寺栄螺堂ホームページ<外部リンク>
| 指定区分 | 国指定重要文化財[建造物(建築)] |
|---|---|
| 指定年月日 | 平成30年12月25日 |
| 所在地 | 太田市東今泉町165 曹源寺栄螺堂 |
地図の読み込みに関する問題が発生したとき<外部リンク>