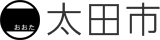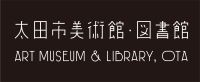本文
毛里田かるたの遊び方
競技上の心がけ
このかるたで遊ぶときは、勝負にばかりこだわらないで、心のふれ合いを大切に、仲良く、礼儀正しくルールを守って競技しましょう。
競技のしかた
競技種目
- 個人競技
一人対一人で勝負する。 - 団体競技
三人が一組となり、二組で勝負する。
競技に用いる札
読み札、取り札とも44枚
競技に必要な係
- 競技進行係 1名(読み手が兼ねてもよい)
- 読み手 1名
- 審判員 各コートに1名
競技の準備
- 団体戦
- 3人ずつ向かい合って1列に並ぶ。陣の幅は1.5メートル以内とし、ひざをそろえてすわる。
- 個人戦
- 1人ずつ向かい合い、並べる札の幅を50センチ以内とする。
- 持ち札
- 進行係の合図でジャンケンをし(団体戦では、まん中の人がする)、勝ったものが取り札をよく切って、22枚ずつに分け、前に置く。
- ジャンケンに負けた者が先にどちらかを取り、勝った者はあとから取る。
- 札の並べ方
- 自陣の前に、団体では2段、個人戦では3段にそれぞれ平均的になるように並べる。
- 両方の陣の間は3センチはなし、各段の間と左右の間は1センチほどあける。
- 並べ方にいろいろ工夫を加えてよい。ただし、団体競技の持ち札は3人で平等になるように並べること。
- 記憶時間
- 取り札を並べてから3分間ほど記憶する。
競技
- 読み手が、空札(からふだ)を2回読む。
空札は、「たのもしい、あしたをきずく毛里田の子」の札を使い、3回目に読む札から取り始める。
その後は、今取った札を予令としてくり返して読み、次の札に移る。 - 競技中は勝手に札の位置を変えてはいけない。札の位置を変えたい時は、相手の了解を得る。
- 取り札が最後の2枚になったら、横に30センチはなして並べ、それぞれの代表1名ずつでこの札を争い1枚を取った者が残りの1枚も取る。
※読み手は、最後の2枚の中に「た」札を入れないこと。 - 札を取るときは、押さえても、はじいても、押しても、引いても、とばしてもよく、札に早く指がふれた方が、勝ちになる。
採点
- 得点の計算は、1枚1点
- 団体競技では「やく札」があり、そろわなければ1枚1点だが、「あ」「た」「て」「ひ」「も」の「毛里田」のつく札3枚がそろったら、10点とし、5枚そろったら、20点とする。
- 個人競技、団体競技とも、同点の場合は、「た」のある方を勝ちとする。
競技上の注意
- 競技の始めと終わりには、おたがいに「礼」をする。
- 対戦中
- 両手を使ったり、札の上にかぶさったりしない。
- 使う手は、札が読まれるまでは、ひざの上に置くか、ひざがしらより前に出さない。
- 自分の陣でも、相手の陣でも読まれた札のない方に手をついたら、「お手つき」として取った札の中から1枚を相手にわたす。
- 味方の3人が同時に「お手つき」しても、相手にわたす札は1枚でよい。
- 両方の手が重なったら、下の者が取る。
- 同時の時は、その札の陣の者にゆずる。ただし、それが「やく札」の時には、「審判あずかり」とする。
- 最後の2枚で「あいこ」の時は、敵味方1枚ずつ分け合う。
- 相手に対し、不満があっても直接言い争いをしないで、審判を通じて話し合うこと。