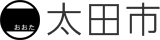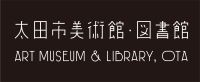本文
徳川館跡の伝新田義重の宝塔

この宝塔は義重の宝塔と伝えられ、天神山凝灰岩(みどり市笠懸町産出)で造られています。基礎・塔身・屋蓋からなり、相輪部は、別に保管されています。塔身の平面は円形で、上に首部をつくり、四角の屋根(屋蓋)の上に相輪をたてています。高さは、総高115cm、屋蓋30cm、塔身47cm(首部含む)、基礎38cmです。
現在は、宝塔1基と基礎の1個が残存しており、各塔の下から1個ずつ瀬戸窯焼製の灰釉四耳壺が出土しました。これらは宝塔と同じ鎌倉時代のものです。
屋蓋を修復した金タガには、「天保八丁酉年(1837)七月」の刻名があります。この宝塔が所在する場所は、徳川氏の館跡と伝えられ、徳川氏が去った後は正田氏が居住し、徳川幕府から特別な地位を与えられ、徳川郷を管理していました。
| 指定区分 | 市指定重要文化財[石造文化財] |
|---|---|
| 指定年月日 | 平成元年2月1日 合併に伴い、平成17年3月28日に改めて新市の文化財として指定されました |
| 所在地 | 太田市徳川町388-6 徳川東照宮 |
地図の読み込みに関する問題が発生したとき<外部リンク>