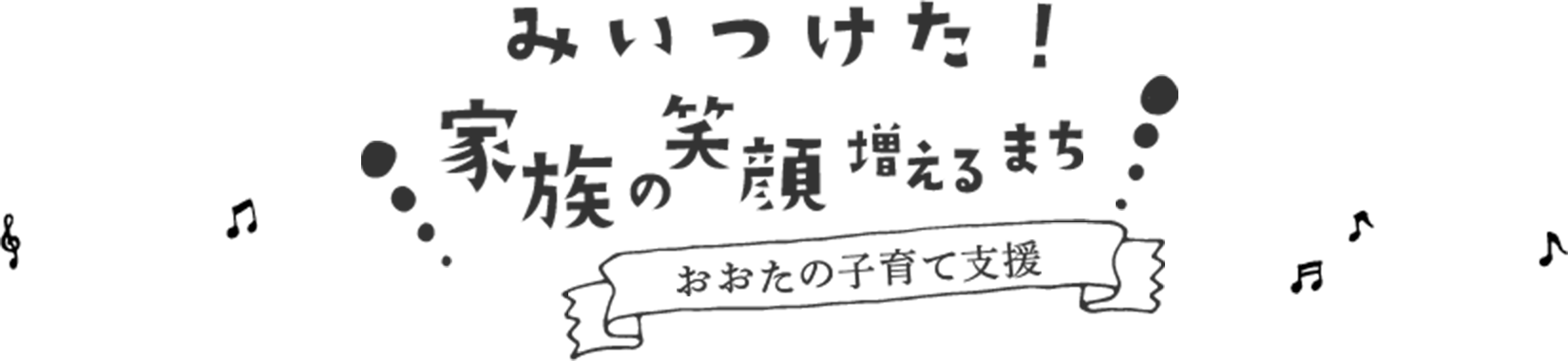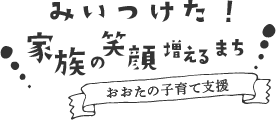本文
太田市のこども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)
こども誰でも通園制度の利用の流れ
こども誰でも通園制度の利用を希望する方は、以下の流れに沿って手続きを進めてください。
Step1 太田市への利用登録オンライン申請
まずは太田市への利用申請が必要です。本ページをよく読んだあと、「こども誰でも通園制度総合支援システムポータルサイト」よりオンラインで利用登録の申請をしてください。
申請後、太田市により利用資格の確認と認定を行います。1〜2週間程度で次の「Step2アカウント登録」のためのメールが届きます。
Step2 「こども誰でも通園制度総合支援システム」へのアカウント登録
こども誰でも通園制度を利用するためには、「こども誰でも通園制度総合支援システム(以下、支援システムと言います)」への登録が必要となります。
事前面談や利用の予約、時間管理、登降園管理など、全て支援システムより行います。
太田市への申請後1〜2週間程度で支援システムのアカウント登録メールが届きます。メールの内容に従って、アカウント登録手続きをお願いします。
Step3 利用する施設への事前面談
支援システムから、利用を希望する施設への事前面談を予約し、実施してください。
事前面談を行った施設のみ、利用が可能です。
なお、事前面談の結果、お子様の健康状況等により安全に通園いただくことが難しい場合は、ご利用をお断りする場合があります。
※事前面談の予約は支援システムからのキャンセルができませんので、施設に直接連絡してください。
Step4 利用開始
支援システムより施設の日時を予約し、利用してください。
※実施施設によって利用開始日が異なることがあります。
こども誰でも通園制度について
こども誰でも通園制度の概要は、こども家庭庁のホームページをご確認ください。
こども家庭庁ホームページ:こども誰でも通園制度について<外部リンク>
こども誰でも通園制度を利用できる方(令和7年度)
以下の全ての要件を満たす方が、太田市内の施設が実施する「こども誰でも通園制度」の利用ができます。
- 保護者・利用する児童ともに太田市内に住民票がある
- 利用する児童の年齢(月齢)が、6ヶ月〜満3歳の前々日まで
- 児童が市内外の保育所、認定こども園、幼稚園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設に通っていない(子育て支援センター、一時預かり、認可外保育施設は除く)
- 認定決定・アカウント登録後の施設ごとの事前面談を実施している
太田市内の実施施設(令和7年度)
| 施設名 | 住所 | 電話番号 | 開始予定 |
|---|---|---|---|
| 大原保育園 | 大原町1283 | 0277-78-2105 | 令和7年12月 |
| とりやまこども園 | 鳥山中町1074-5 | 0276-25-4079 | 令和7年12月 |
| 太田いずみ幼稚園 | 東今泉町801-1 | 0276-37-3245 | 令和7年12月 |
- 利用予約の管理については各施設が行います。ポータルサイト上での各施設の予約開始時期については、施設へお問合せください。
- 利用にあたって、お子さまに配慮が必要なことその他ご不安な点がありましたら、直接施設へご相談ください。
利用方法、利用料金
利用にはシステムからの予約が必要です
支援システムより利用を希望する施設、利用日時の予約が必要です。
支援システムや個別の端末の操作方法については太田市では回答できませんので、システムのコールセンターへお問い合わせください。
利用時間
- こども一人当たりの月の利用可能時間は、10時間が上限です。
- 利用枠は1時間の単位です。1回あたり最低1時間から利用できます。
- 当該月の余り時間分を翌月以後に繰り越したり、翌月以後分を繰り上げて利用することはできません。また、他のこどもへ付与することもできません。
- 利用時間は支援システム上で管理されます。
利用料金
利用料金は児童一人あたり、1時間300円です。
- 給食やおやつの提供など、施設や活動内容によって利用料金の他に追加で実費がかかることがあります。施設との事前面談の際によくご確認ください。
利用のキャンセル(キャンセルポリシー)
予約をキャンセルする場合、キャンセルポリシーが適用されます。
キャンセルポリシーの詳細をご確認ください。太田市こども誰でも通園制度の利用に関するキャンセルポリシー [PDFファイル/440KB]
- 施設によって取扱が異なることもありますので、合わせて利用施設にも必ずご確認ください。
- 実際に利用していなくても、キャンセルによって月の利用可能時間から減算を行うことがあります。キャンセルポリシーをよくご確認ください。
支払い方法
利用する施設に直接、施設の示す支払い方法によりお支払いください。
利用料金の減免
以下に該当する方は、太田市への認定申請時に合わせて減免申請を行い、審査によって利用料が減免されます。
審査の中で、追加書類の提出が必要な方は、こちらからご連絡をいたしますので、指示に従って書類を提出してください。なお、その場合でも先に利用登録は行いますので、誰でも通園制度自体の利用は減免決定前に行うことができますが、減免を決定するまでの間は通常の利用料金の支払いが必要です。減免決定後、決定前の利用分を遡っての利用料の返還はできませんのでご了承ください。
| 対象者 | 利用料負担額(こども1人、1時間あたり) | 提出が必要な書類 |
|---|---|---|
| 生活保護法による被保護世帯 | 0円 | 生活保護受給者証 |
| 市町村民税非課税世帯 | 60円 | (一部の方)所得課税証明書など※1 |
|
市町村民税所得割合算額が77,101円未満である世帯(世帯年収およそ360万円未満の世帯)※2 |
90円 | (一部の方)所得課税証明書など※1 |
| 要支援児童及び要保護児童のいる世帯、その他市が特に支援が必要と認めた世帯 | 150円 | 事前の相談が必要です※3 |
※1 保護者・同居の祖父母の全員の個人市町村民税額により審査します。太田市での住民税が課税されていない方は、該当の市区町村での「所得・課税(非課税)証明書」の提出が必要です(令和7年1月1日に太田市内に住所があった方の分は提出不要です)。令和7年度中の申請においては、令和7年1月1日に太田市に住所が無い方について、「令和7年度 所得課税(非課税)証明書」を申請時に提出してください。取得方法は各自治体にお問い合わせください。令和7年1月1日に国内に住所が無かった方については、海外での収入を含めて「収入申立書」の提出が必要です。様式はこちらのページにある「令和7年1月1日に国内に住所がない方の申立書 」を使用してください。
※2 住宅ローン控除・寄附金控除等の税額控除前の金額により計算します。
※3 公的機関により、支援が必要なことの客観的な確認が必要です。該当の方で減免を希望する場合は、必要な書類等を確認しますのでご相談ください。
審査の結果について
認定証において、減免決定された場合はその減免区分と期間が表示されています。審査の結果、減免が認められなかった場合は、「減免区分:非該当」と表示されます。
認定証はこども誰でも通園制度ポータルサイト上で確認できます。
減免の更新手続きについて
毎年7月〜8月に、9月以降も引き続き利用料の減免を受けるための更新手続きが必要です。手続きが必要な方はこども課からご案内いたします。
なお、市町村民税非課税世帯、世帯年収360万円相当の世帯での減免対象の方は、参照する市区町村民税の課税年度が変わります。新たな年度の税額により減免の対象から外れると、9月分からは通常の利用料金となります。
利用登録オンライン申請
支援システムポータルサイト(こども家庭庁)<外部リンク>より利用申請を行う
申請前にこちらの「太田市誰でも通園制度の確認事項」 [PDFファイル/578KB]を必ずお読みください
ポータルサイトから利用申請を行った場合、上記について確認・同意したものとみなします。
オンライン利用申請方法
- こども家庭庁の支援システムポータルサイト<外部リンク>を開く
- ページ中段の「まずは利用申請から!」から、「群馬県」→「太田市」を選択し、「確認する」を押す
- アカウントを登録するメールアドレスを入力し、「申請する」を押す
- 入力したメールアドレスに、登録用のフォームURLが届くので、画面の指示に従って必要事項を入力し、申請する。
※ポータルサイトの利用方法や個別のスマートフォン端末の使用方法等について、太田市では回答できませんので、ポータルサイト上のコールセンターへお問い合わせください。

オンライン申請後
オンライン申請が完了した後、太田市で利用決定、認定の決定を行います。
1〜2週間程度で、入力したメールアドレスに決定の通知が送付されます。その後、メールの指示に従ってアカウント登録を行い、事前面談、利用を開始してください。
※審査が間に合わず利用ができないことがありますので、満3歳直前の子どもを申請する場合はご了承ください。
申請の却下について
申請された内容について太田市で審査した結果、申請の不備等で利用・認定を却下した場合には、却下した旨の通知が入力したメールアドレスに届きます。
却下の内容についても記載されますので、必要に応じて再度申請を行ってください。
ご注意ください
以下の場合等には申請が却下になりますので、申請フォームの入力の際はご注意ください。
- 満3歳以上の子どもを申請した場合
- 既に保育園に通園しているなど、要件を満たさない子どもを申請した場合
- 保護者、申請する子どもの住所が太田市に無い場合
※複数の子どもの申請する場合、一人でも要件を満たさない場合は、申請全体が却下となります。他の子どものみ申請する場合は、申請をやり直す必要があります。
「利用料減免の申請の有無」を「有り」で申請した方
減免申請の審査にあたり追加の書類提出が必要な場合は、こちらからご連絡します。
なお、その場合でも誰でも通園の利用決定は減免決定より先に行いますので、通常の利用料の支払いにより施設を利用することができます。減免決定前に遡って利用料の返還はありません。
追加の書類提出が不要な方は、利用決定と減免決定を同時に行います。
減免の決定について
認定証において、減免決定された場合はその減免区分と期間が表示されています。審査の結果、減免が認められなかった場合は、「減免区分:非該当」と表示されます。
認定証はこども誰でも通園制度ポータルサイト上で確認できます。
オンライン申請が難しい方、事前の相談が必要な方
以下に該当する方は、太田市役所3階こども課窓口にご相談ください。
- パソコンやスマートフォン、メールアドレスをお持ちでなく、支援システムの利用が難しい場合
- 要支援児童及び要保護児童の居る世帯の減免申請を受けようとする場合
- 利用にあたり、児童に対し医療行為が必要な場合(医療的ケア児) ※医療的ケア児の受け入れが可能な実施施設は現在ありません。
利用登録後の手続きについて
以下の場合は、手続きが必要です。太田市役所こども課入園児童係までご相談ください。
- 太田市から保護者・児童が転出する
- 児童の世帯員に変更がある
- 新たなお子さまの利用を申請する
- 新たに減免の申請を行う