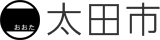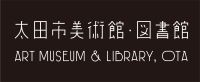本文
冠稲荷神社 本殿、拝殿、聖天宮 3棟 附 棟札 8枚
冠稲荷神社(かんむりいなりじんじゃ)は、天治2年(1125)、新田義重の父である源義国によって創建されたと伝えられる古社です。社伝によると、「承安4年(1174)、源義経は藤原秀衡を頼り奥州下向の途中、この神社に参籠した際、源氏ゆかりの神社と知り、冠の中に奉持してきた伏見稲荷大明神ほか2社の御分霊・神礼を社に納めた」という故事により、以後、神社は冠稲荷大明神と呼ばれるようになったとされています。
本殿は、三間社流造といわれ、正面に千鳥破風、向拝は軒唐破風の造りになっています。彫刻も極彩色で彩られており、大変見事な造りとなっています。棟札から享保7年(1722)12月に上棟されたことがわかります。
拝殿は、正面(10.18m)、側面(7.64m)、入母屋造の平入で正面に千鳥破風、向拝は軒唐破風としています。背面には正面(4.54m)、側面(5.70m)の切り妻の幣殿を設け、本殿とは接続しておりませんが、社殿として権現造に準ずる形態を示しています。建築当初の平面形式は、棟通りを境にして、裏側を建具で仕切った畳敷きの屋内礼拝所とし、表側を板張り床のままとして土足で上がる吹き放ち空間の向拝部分にしたものです。これは県下でもめずらしく、古風な拝殿の平面形式を示しています。天井は、屋内礼拝所及び向拝部分とも格天井(ごうてんじょう)で、極彩色の花鳥絵が描かれています。また、屋内礼拝所の中央部の天井は鏡天井となり、下田島在住の交替寄合格の旗本「新田源朝臣道純(にったみなもとあそんみちずみ)」(岩松満次郎道純)によって描かれた立派な龍の墨絵が残されています。
建築様式や細部の手法に江戸時代中期の特徴をよく表現しており、建造後の改造も少なく、保存状況も良好です。本県における江戸時代中期を代表する拝殿建築として極めて重要なものです。棟札から寛政11年(1799)に上棟されたことがわかります。
聖天宮は正面(2.89m)、側面(3.88m)と比較的小規模な建物でありながら屋根が複雑で、四方入母屋造正面唐破風付という特徴的な造をしています。棟札によると、安政4年(1857)佐波郡下渕名の宮大工棟梁弥勒寺河内藤原照房(弥勒寺音次郎)の製作です。天井と周囲の彫刻は音次郎の子音八とその弟子の諸貫万五郎によるもので、常陸(茨城県)の天引観音や笠間稲荷神社本殿などの建築に携わった名彫工の技の冴えを垣間見ることができます。


冠稲荷神社の本殿 冠稲荷神社の拝殿

冠稲荷神社の聖天宮
| 指定区分 | 県指定重要文化財[建造物(建築)] |
|---|---|
| 指定年月日 |
【冠稲荷神社の本殿・聖天宮】 昭和47年9月26日
【冠稲荷神社の拝殿】 平成2年3月26日 |
| 所在地 | 太田市細谷町1 冠稲荷神社 |