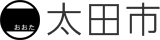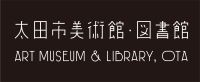本文
太田かるた
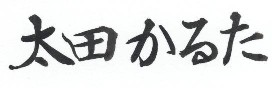
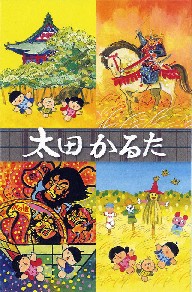
原画 童絵作家 池原 昭治氏(狭山市在住)
題字・揮毫 太田市書道連盟理事長 本城 亮俊氏
太田市では、市民憲章の一環として、郷土への理解を深めてもらう運動のため、「太田かるた」を作成いたしました。
地域性を考慮し、歴史・人物・施設など太田市にふさわしい読み札を市民公募した読み札994点の作品のなかから44点を、太田かるた作成委員会が選考し作成しました。
作成時期 平成18年11月発行
販売価格 1組 500円(税込み)
販 売 先 市民そうだん課窓口(市役所3階)、太田市美術館・図書館、道の駅おおた
| あ行 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| あ | アジサイと 百観音の さざえ堂 | い | いざ鎌倉 義貞挙兵の 生品神社 | う | 運動公園 家族みんなで スポレク祭 |
| え | 江戸めざし 献上松茸 進み行く | お | おいしいな 藪塚名産 紅小玉 | ||
| か行 | |||||
| か | 金山の 歴史を語る 大ケヤキ | き | 木崎宿 語り継がれる 色地蔵 | く | 群を抜く 工業生産 県下一 |
| け | 毛野国 誇る古墳は 天神山 | こ | 子育てと 臥龍松の 大光院 | ||
| さ行 | |||||
| さ | 桜咲く 春の八瀬川 花吹雪 | し | 市民憲章 人と心と まちづくり | す | 雀まで そっと見に来る かかし祭り |
| せ | 政治家で 飛行機王は 中島知久平 | そ | 育てよう 未来に羽ばたく 太田っ子 | ||
| た行 | |||||
| た | 大慶寺 綿打郷の ぼたん寺 | ち | 長楽寺 東関最初の 禅文化 | つ | 塚廻り 居並ぶ埴輪 語りかけ |
| て | 出初式 暮らしを守る 消防署 | と | 東照宮 家康まつる 世良田郷 | ||
| な行 | |||||
| な | 夏の夜に 尾島ねぷたの 灯と囃子 | に | 新田荘 歴史に残る 遺跡群 | ぬ | 抜きんでた 幕末の思想家 彦九郎 |
| ね | 粘りなら 尾島名物 やまといも | の | 農工商 未来を拓き 伸びゆく太田 | ||
| は行 | |||||
| は | 母と子の 交流深める 子育てサロン | ひ | ヒマワリと コスモス畑の 花トピア | ふ | 藤棚と 堀が自慢の 反町薬師 |
| へ | ヘビセンター 世界のヘビが 大集合 | ほ | ボケの花 きれいに咲くよ 冠稲荷 | ||
| ま行 | |||||
| ま | 満徳寺 世界に二つの 縁切寺 | み | 明王院 決起知らせた 触れ不動 | む | 昔話 古老が伝える 知恵袋 |
| め | 名湯が 諸病を癒す やぶ塚温泉 | も | 紅葉映え 五輪塔並ぶ 金龍寺 | ||
| や行 | |||||
| や | 八木節の 樽の音ひびく 夏祭り | ゆ | 悠々と 流れる姿 坂東太郎 | よ | 用水の 歴史伝える 岡登 |
| ら行 | |||||
| ら | ラジコンで 飛行機とばす ページェント | り | 龍舞に 豊作祈る 萬燈まつり | る | ルールを守り 楽しく遊ぶ こどもの国 |
| れ | 例幣使 日光詣での 道しるべ | ろ | 老人が いきいき通う 福祉センター | ||
| わ行 | |||||
| わ | 湧き水は 重殿 矢太神 国史跡 | ||||