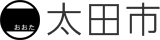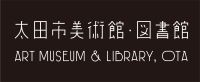本文
電気に関連する火災にご注意を!!
今年も電気に関連する火災が多発しています!
太田市消防本部管内で毎年出火原因の上位
消防本部管内では、今年も電気に関連する火災が多く発生しています。特に夏場はリチウムイオン電池の使用や保管方法に注意が必要です。
私たちの暮らしに欠かせない電気も、使い方を誤ると火災につながってしまいます。電気の使い方や電気火災の内容を理解して、電気に関連する火災を防ぎましょう。
電気に関連する火災の主な原因と対策
◎ 充電式電池 (リチウムイオン電池)
1.衝撃・過度な力/水気を避ける
・モバイルバッテリーは、精密機器のため衝撃や水気は禁物です。
・落下による破損、浸水したモバイルバッテリーが発火するケースがあります。
【対策】→損傷や変形したリチウムイオン電池は使用しない。
2.加熱・冷却
・モバイルバッテリーは、高温の場所に弱い性質があるため、使用・保管方法にご注意ください。
・モバイルバッテリーが暖房器具の温風により加熱されたり、発熱したモバイルバッテリーを冷却
目的で冷蔵庫へ入れて発火や煙が発生するケースがあります。
【対策】→リチウムイオン電池は熱さや寒さに弱いため、適切な温度・場所で使用や保管をする。
→夏場、車内放置や直射日光が当たる場所への放置はやめましょう。
3.その他の留意事項
・充電する際は、対応した充電器を使用する。
・充電式電池に膨張、異臭、発熱、変色など異常が見られる場合は、直ちに使用を中止する。
・危険ごみは、分別ルールや収集日を確認し、正しくごみを出しましょう。
4.危険ごみの正しい捨て方(産業環境部 清掃事業課)
◎ テーブルタップ、プラグ、コードなど
1.コードの半断線
・コードが家具に踏みつけられたことで出火に至るケースがあります。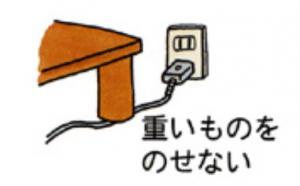
【対策】→ コードに重いものが載っていないか確認する。
・コードが折り曲げて使用されていたため半断線となり
出火に至るケースがあります。
【対策】→ コードは無理に折り曲げて使用しない。
2.テーブルタップ・コードの定格容量を超えた使用
・延長コードに複数の使用電力が大きい機器(ドライヤー・暖房機器等)を接続し、

定格容量を超えた使用をしたことにより出火に至る
ケースがあります。タコ足配線等。
【対策】→ テーブルタップは許容電力内で使用する。
異物が入りやすい状態で使用しない。
3.コードを束ねた状態での使用(ジュール熱の発生)
・コードを束ねた状態で、使用電力が大きい機器を接続し、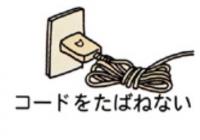
使用することで出火に至るケースがあります。
【対策】→ コードを束ねた状態では使用しない。
4.接触不良
・コンセントにプラグを不完全な状態で差し込み使用したことで出火に至るケースがあります。
【対策】→ 定期的にプラグの状態を点検し、プラグが抜けかけていないか確認する。
5.清掃不良・異物の浸入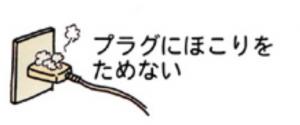
・コードのプラグ及びコンセントの差し込み口部分に、
清掃不良により埃などが付着するこ とで、トラッキングが
発生し出火に至るケースがあります。
【対策】→ 定期的にプラグを点検・清掃する。
・コンセントの差し込み口部分にコップの水をこぼす・子供が異物を挿入することにより、
トラッキングが発生し出火に至るケースがあります。
【対策】→ 水がかかる場所では使用しない。異物が入らないよう保護キャップを使用する。
6.その他の留意事項
・プラグを抜き差しする際にコード部分を持って引き抜く、プラグに負荷が掛かるなど、
プラグの変形やコードが損傷するような使用をしない。
・紫外線等の影響により被覆の劣化が早まる可能性があることに注意する。
・異物の浸入を防ぐために保護キャップは有効であるが、一方で乳幼児が取り外し、
口に 入れてしまうなどの事例も発生している点に注意する。
◎ リチウム電池
1.絶縁処理未実施での保管(維持管理不良)
・ごみ箱に廃棄されたリチウム電池が電池同士で接触することで短絡し、出火に至るケースが
あります。
(使い終わった電池でも、絶縁をせずに廃棄をした場合に火災に至るケースがあります。)
【対策】→ 電池は端子同士が接触しないように保管する。廃棄時は絶縁する。
◎ 電子レンジ
1.過熱・誤加熱
・食品(さつまいもや肉まんなどを想定)が過熱により出火に至るケースがあります。
・アルミ箔で包装された食品を電子レンジで加熱し出火に至るケースがあります。
【対策】→ 加熱中はその場から離れない。取扱い説明書に従って使用する。
2.清掃不良
・電子レンジの庫内に多量の油脂が付着した状態で使用したため出火に至るケースがあります。
(火を使わない電子レンジであっても、過熱・清掃不良により出火の可能性があります。)
【対策】→ 電子レンジの庫内は定期的に清掃する。
太田市消防本部 火災予防啓発動画
太田市消防本部では、「電気に関連する火災を1件でも減らしたい」そんな思いから火災予防のための動画を作成して公開しています。身近に潜む火災リスク。是非、下記リンクから確認してください。