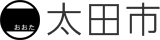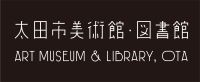本文
令和6年8月15日号こんにちは市長です
「お蚕(かいこ)さま」というくらい蚕は農家の生計を支えた。私が子どもの頃の祖母たちの世間話を覚えている。「養蚕をやっている家には嫁に行かせたくないねー」。農家の嫁は即労働者になる。春秋に蚕の面倒を見て、それに田植え、稲刈り、麦の収穫まで。子どもを産み乳を飲ませ、成長させるのは嫁さんの仕事。大きな農家に嫁ぐというのは苦労を抱えて生きるということだった。今では考えられないような話である。
江戸時代の岩松の殿様が120石取りだった頃の話。殿様は今の県立フレックス高校辺りに館(やかた)をかまえていた。120石では家臣を2、3人しか持てない。領地の農家に家臣を兼務してもらったり、年貢を集めるのもご近所の代官にお願いしたりしていた。どう考えても年に一度の年貢では殿様の家族を養うのに精いっぱい、何か副業をしなければならなかった。「うちのお殿様は絵がうまい」と、江戸中期の岩松義寄(よしより)は町民や農民の間で評判になった。特に猫の絵が売れた。「芸は身を助(たす)く」です。血筋というのがあるんですかね、義寄の跡継ぎ、徳(よし)純(ずみ)は多い月に300枚も描いたと言われている。今の金額にするとざっと500万円も稼いだことになる。そして、岩松4代に継がれた「新田猫絵」というブランドができたのである。その裏には殿様の側近の苦労があった。「養蚕農家の皆さん、お蚕さまの天敵ネズミは新田猫にお任せください。殿様の描いた新田猫を掛け軸にして飾っておけば、たちまちネズミは退散します」。フェイクニュース?である。まさか掛け軸を見たネズミたちが一目散で逃げ出すなんてありっこないですよね。ネズミを退散させたという新田猫絵は世良田にある新田荘歴史資料館で見られます。
その新田猫が合併20年を機に、「まだまだのびざかり」の太田市のマスコットキャラクターとして登場します。ネオタ(NEOTA)で~す。 (8月1日 記)
※詳しくは9月1日号「広報おおた」で紹介します。