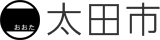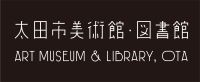本文
令和6年9月15日号こんにちは市長です
この間、総務省に行ってきた。どうしても「ふるさと納税」がすっきりしない。すっきりさせたいと思って担当課長に疑問点を指摘したが、それらしき答えはなかった。質問書を渡してきた。
憲法30条「国民は・・・納税の義務を負ふ」とある。税は、国や地方公共団体を維持し、発展させていくために欠かせないのだ。所得税などの国税は日本政府に、地方税はその居住する県、市町村に納める。太田に住む人が県民税を栃木県に、市民税を熊谷市になんてことはあり得ない。税を納めてもらうことで、行政サービスを提供することができる。当たり前である。が、「ふるさと納税」は他のまちに納税(税から寄付)して、自分の住むまちから行政サービスを得る。税と行政サービスは対であるという憲法30条の意味は失われる。川崎市は135億円もの市民税が失われているという報道があった。太田市でも5億円にまで増えた。とはいえ、ゴミの回収を減らしたり、防災で手を抜いたり、学校給食の無料化を止めてしまったりできるはずもない。当面、国が75%まで穴埋めしてくれているが、明日の保証はない。
「ふるさと納税」の約20%は仲介業者などに納税? される。市民税の一部が手数料として事業者に支払われる。事業者に払うのを「納税」と言えるのだろうか。税は議会で審議され、使途が決められる。さとふる、ふるなび、楽天などは年末が近づくと、テレビに雑誌に宣伝合戦をする。原資は市民税。市民税が業者のテレビ広告に化けてしまう。議会も市側も知らないところでやっている。とんでもない話だ。そして、北海道のM市などのようにお金がじゃぶじゃぶ状態のまちが出現する。お金があふれて貯金に精を出すことになる。「ふるさと納税」は1兆円を超えた。憲法が泣いている。
税を払ってホタテやお肉をもらうのが当たり前、税をゆがめた姿に変えてしまっている。「税? 払うよ。それで何くれるの? 」 (9月2日 記)