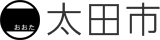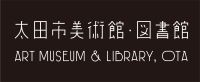本文
令和6年10月15日号こんにちは市長です
9月に大学の同窓会の知らせが届いた。60年も前のことなのに、断片的にではあるがあの頃の記憶がよみがえってくる。みんな仲が良かった。そういえば、日本経済新聞のコラム「交遊抄(こうゆうしょう)」に学生時代のことを書いたことを思い出した。スクラップがあったので紹介したい。
目立たない大学生だった。周りは育ちのいい慶応生、群馬の田舎育ちの私。言葉にできない焦りも抱えた学生時代だったが、商学部の片岡一郎先生のゼミで学んだことは大きな財産になった。40年前(今では60年前)、マーケティングはまだ珍しい学問だった。企業のケーススタディーを中心にした授業で印象に残ったのは「ミニスカートを日本で売る戦略」。当時、日本にミニスカートはなかった。誰も見たことのない商品を、消費者の隠れた欲求を刺激して新しい価値を創造するマジックに魅せられた。ハーバード帰りで洗練された先生が話す理論は、何もかもが新鮮に思えた。先生は放任主義だったし、私も特に積極的ではなかった。教壇越しの片思いのように、一方的に影響を受けた。何事もサービスの受け手の視点から発想する癖は、県議時代から私を支配している。注目された行政改革や英語教育特区の遠い生みの親だ。年2回、先生を慕う「3K会」が開かれる。ゼミ3期生の「3」と先生の頭文字の「K」が由来だ。元東レ研究所取締役の大橋清君をはじめ、大手企業で活躍してきた仲間との懇談は、まだまだ頭の固い政治の世界においてはアイデアの宝庫。良き師と相談無料の優秀な「シンクタンク」に恵まれた私は幸せ者だ。
日本郵船の友人が「にっぽん丸を使えば!」というアドバイス。500人の子どもたちを5年続けて小笠原に旅させた。行革を目に見える形で子どもたちに還元できた。「3K会」は久しぶり、見ても分からぬ顔ばかりだろうな。 (9月30日 記)